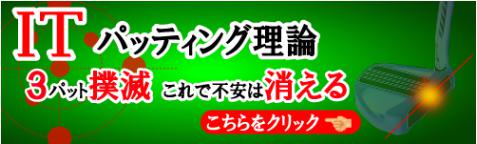「パットの距離感をスイングの振り幅で合わせる」主旨の記事を目にした方は多いのではないでしょうか。
当サイトでも紹介しており、距離感を合わせる方法のひとつではあるのですが…
「このやり方はNG」とする主張もあります。(こちらのほうが多数派かも?)
森守洋コーチが著書「苦手を得意に変えるパッティング」で、「振り幅はNG」な理由を解説されています。
・ゴルフ【苦手】を【得意】に変えるパッティング(Amazon・PR)同書の74~76ページから一部を抜粋して紹介します。
タイガーウッズは振り幅は変わらない 変わるのはスピード
森コーチはタイガーウッズ選手の例を挙げています。
どんな距離でもストロークの振り幅が変わらないと決めつけるのは早計かもしれませんが、タイガー・ウッズは決して振り幅の大きさで距離感を加減しないということです。
実際は少し変わるとはいえ、タイガーの1メートルと5メートルのパットの振り幅はほぼ同じなのです。
パットのレッスン書などには「振り幅で距離感をコントロールする」とよく書かれていますが、タイガーに限らず、どんなプロでも振り幅で距離を合わせているわけではありません。
それでは何が変わるのかというと…
振り幅が変わらないなら何が変わるのかというと「スピード」です。力の出し具合をコントロールしたいと思ったら、誰でも本能的にスピードが変わります。
右手に丸めた紙などを持ち、下手でトスするようにゴミ箱に向かって投げるとします。ゴミ箱が1メートル先の場合と、5メートル先では腕の振りがどう違うでしょうか。
1メートルなら腕をゆっくり振り、5メートルでは少し速めに腕を振るでしょう。腕を振る大きさが多少は変わっても大きな差はないはずです。
振り幅と距離を関連づけると、スイングそのものが変わりかねません。
距離によって振り幅を変えるという考え方は、5メートルの距離なら10メートルの半分とか、下手すると1メートルは5メートルの五分の一の振り幅、あるいは5メートルは1メートルの5倍の振り幅という具合に安易に考えがちです。
振り幅を意識すると別のリスクもあります。
振り幅を意識するとインパクトが緩む
振り幅で距離を変えるスイングはインパクトが緩むリスクがあるのです。
こうした方法が間違っているとはいいませんが、自分の感覚を無視してしまうことになり、かえって距離感が合いにくいのは事実です。
それに振り幅で距離感を出そうとすると、インパクトが緩んでしまいがちです。
テークバックが大きすぎて、インパクトでヘッドを減速したり力を弱めたりしてインパクトが緩むと、フェースの向きが変わりやすくなります。
それだけフェースのスクエア感覚が失われて、出玉の方向が安定しにくいのです。
逆にテークバックが小さすぎてダウンスイングに入った途端に急いでしまうパターンもあります。この場合もフェースの管理が難しくなり、方向性と距離感の両面でミスが発生しやすくなります。
それではどのような意識で練習すると良いのでしょうか?
振り幅は同じでストロークの速さを変える練習で「縦カン」を磨く
森コーチは「振り幅を変えずにストロークのスピードを変える」練習を勧めています。
目と手の共同作業を繰り返して「縦カン」を養うのです。
「縦カン」とは「距離感と曲がり幅、スピードの複合イメージ」のことです。
大きすぎて緩む。小さすぎて急いでしまう。
こうした症状を自覚している人は、ストロークの振り幅を一定にして、全体のスピードを変える練習をするといいと思います。
結局のところ、距離感というのは頭で考えるものではないのです。
縦カンを身につけているつもりの人でも10メートルのパットを打つときに「10メートルはこのくらいの振り幅で打つ」とか「5メートルの2倍の大きさで振る」などと頭でイメージするだけでは、距離感はなかなか合いません。
カップまでの距離を見て縦カンを働かせながら素振りし、「このくらいかな」と目から得た情報を元にして、ストロークのスピードを調整するのです。
これが私のいう目と手の共同作業というわけです。
「パットの距離感を振り幅で調節するのはNG」とする記事は他にも作成しています。
お時間があったらご覧ください。